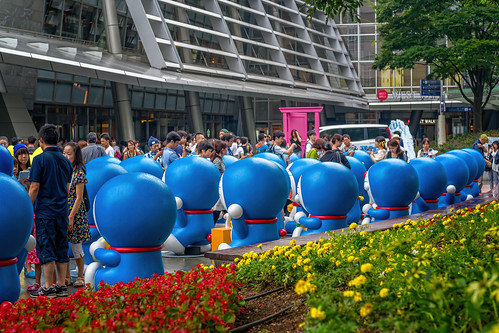一眼レフ用NIKKOR標準レンズのFからF2時代の代表選手のようなレンズ。これ以前Fの初期にNIKKOR-S銘で9枚羽のレトロフォーカスタイプがあるけど本流とはならず。NIKKOR-H 50/2はその後も引き継がれて行く生え抜き代表選手。
カラフルな墨入れは見て楽しい。ヤレるどころか半世紀経ってむしろ赴きが増す。ニコンさんにはノベルティで今時のレンズのビヤジョッキや、マグカップより、陶器でこんな湯呑茶碗を作って欲しい
よ。

フィルムで使ってた印象では、同時代の大口径標準のF1.4が軒並みバリバリ過剰補正の開放ホンワリ玉なのに対して、50/2は端整で優等生な印象だったが、α7で使うとどんな感じでしょうね。
アダプターでボディから遠く離れた蟹ツメが銃の照門みたい。

開放 - α7、JPEG
開放での後ボケはリンギング、二線ボケ、共にあるが、均一で像が崩れて流れる感じは無い。ピント面は開放からキレがある。前回のSUMMICRON-R 50/2の方が像の流れは多い位。

F8 - α7、RAW>Lightroom>PhotoShop
何時もカブの整備でお世話に成ってるバイク屋さん。遥々遠くまでピックアップしてもらったり助かってます。行くと「そろそろ買い替えじゃ無い」とウルサイけどね。「目指すぜ!20万キロ!」。
都心でこんな風にポツンと感がある建物は珍しい。
都心でこんな風にポツンと感がある建物は珍しい。
F8 - α7、RAW>Lightroom>PhotoShop
 >
>F8 - α7、RAW>Lightroom>PhotoShop
立ち食い蕎麦を食べにワザワザ足を運んだ西葛西。目当ての蕎麦屋は休みだった・・・ ブラブラ歩いて気づいた、西葛西には3桁局番の看板が数多く残ってた。電話番号は7桁が覚えるのにリズムが良い。8桁覚えにくい。

F8 - α7、RAW>Lightroom>PhotoShop
久しぶりに近所の公園を抜けようとしたら、通れた所が通れなく成っていた。この状態は明らかにハッピーな状態では無いな。話拗れてしまってるのが良くわかります。あ~切ない。>と、くだらない話ばかりで、全く写りの事に言及しないのは、ご覧の通りに語る事無く写るから・・・
とは言いながら、今回は特に前回のSUMMICRON-R 50/2と較べて思う事は凄くあるのだが、情緒的な話になりそうで、上手く文に出来ないので語らない。否、語れない。

とは言いながら、今回は特に前回のSUMMICRON-R 50/2と較べて思う事は凄くあるのだが、情緒的な話になりそうで、上手く文に出来ないので語らない。否、語れない。

F8 - α7、RAW>Lightroom>PhotoShop
機械や道具、人の作った物を話そうとすると、最後は情緒的な話に詰る。それは恐らく、間違いなく存在する違いを、何が違うのか理解出来ず、更には違いを的確に表現する抽象的な言葉を持ってないから情緒になっちゃうんだよ。。。きっとね。
「官能的な写り」とか「味わい深い」などと、少なくとも文にはしたくない。(使っちゃうかも知れないけど・・・・)でも、クオリティって意味の画質とは異なる違いは感じてるのですよ。イロイロとね。今回はあらためて上手く言葉に出来ない違いを考えさせらた一本だった。

開放 - α7、RAW>Lightroom>PhotoShop
数日に渡って持ち歩いて撮っても、開放で撮らないんだよ。つくづくとレビューとかに向いてないのだと思う。仕方無いから自宅で飼猫を開放で撮る。開放でもピントは非常に掴み易い。

F2 - F2.8 - F4 - F5.6 - F8 - F11 - F16

F2 - F2.8 - F4 - F5.6 - F8 - F11 - F16
開放は全体にフレアっぽいが大きな破綻無く、素性の良さがうかがえる。絞る程に鮮鋭にF5.6で十分、F8で文句なし。急に周辺が流れるとか、ストンと光量が落ちるとかの癖が無く、周辺減光も画質の変化もなだらか。端整な印象はフィルムで撮った印象と同じ。